こんにちはじろうです。
今回は将棋で、初段になるまでの勉強法などを紹介したいと思います。
こんな悩みを抱えている人もいるんではないでしょうか?
私自身も子供が、初心者で将棋にハマりだしたころ同様の悩みを抱えていました。
なぜなら、やはりまず目指すべき目標は初段と考えていたからです。
ただ、私も素人のため、まったくといって将棋の勉強方法が分かりませんでした。
そこで、将棋教室の先生や先輩親将から色々と教えてもらい、息子と一緒に実践してきました。
そのため、息子が始めたばかりのころからの記録をとってあり、今回はそれを踏まえて解説したいと思います。
息子は、現在小学生で道場三段です(私は道場3級です)
初段を目指す上で色々な勉強などを行ってきました。その中で特に効果のあったものにしぼって紹介したいと思います。
息子は級が、だんだん上がるごとに勉強法も変わってきましたので、
この記事では、棋力ごとに5段階に分けて勉強法やオススメ本を紹介いたします。
| 将棋道場の棋力 | 将棋ウォーズの級 |
| 15級~12級 | 4~5級 |
| 12級~9級 | 3~4級 |
| 9級~6級 | 2~3級 |
| 6級~3級 | 1~2級 |
| 3級~初段 | 初段~1級 |
初段になるまでの、棋力別の勉強方法などがわかります。

道場初段について
目指すべき初段については、私(級位者)からみたらこんな感じのイメージをもっております。
•序盤で大きなミスがない
•受けが強い
•終盤で的確に寄せてくる
•序盤で大きなミスがない

あっ!角のききを見逃して駒をタダでとられた・・・・(´;ω;`)
級位者どうしの対局で、大きなミスとしてよくあるのが角の効きを見逃して、駒がタダでとられ序盤で一気に形勢が悪くなることがあります。やはり、初段になるとほとんどそういった大きいミスを起こさないです。
大きなミスをおかさない!
これも初段になるために必要なことだと思います。
•受けが強い

受けが強すぎて全然寄せれない(´;ω;`)
一番力の差を感じるのは、受けの強さかなと思います。
級位者どうしの対局だと相手の奇襲戦法にハマってすぐに形勢が悪くなることはよくありますが、初段ぐらいの棋力の方に、奇襲戦法を仕掛けても的確に受けられてしまいます。
受けの強さも初段になるために必要なことだと思います。
•終盤で的確に寄せてくる

あれ!いつの間にか逆転されてる(-_-;)
よく、初段ぐらいの方と対局すると、たまに中盤がうまくいって、終盤でこっちの方が優勢になることが稀にあります。
しかし、こっちが寄せでモタモタしているといつの間にか、鬼のような逆襲が始まって一気に寄せられて、詰まされることがあります。
この寄せや詰みなど読みの強さも初段とは力の差を感じるところです。
•子供の初段の実力とは
子供で初段の子は、かなり強いです。
息子の通っている将棋道場でも、小学生で有段の子は大体全体の5%程度です。
低学年3年生までで言うと、低学年の全国大会県代表レベルです。
ただ、しっかりと取り組めば、子供で初段は問題なく到達できる目標です。
子供が将棋初段になるために必要なこと【将棋初心者〜14級、将棋ウォーズ5級】

初心者の内は、一杯対局して将棋を楽しもう。
挨拶などの礼儀も忘れずに!
勉強1:対局をして将棋の楽しさや礼儀を覚える

まわりに対局できる人がいないな!
まずは、とりあえず対局をいっぱいしましょう。
とにかく対局を重ねて将棋の楽しさや礼儀を学びましょう。
いっぱい対局するためには、親や兄弟が一緒に覚えることオススメ致します。親や兄弟が覚えておけば、気兼ねなく将棋をすることができます。
わたしも息子と一緒に将棋を覚えました。
時間があれば、対局をして少しづつルールや戦法などを覚えていきました。
息子と一緒に、覚えることで私自身の棋力も伸びていき少しレベルの高い棋書も理解して、息子に伝えれるようになりました。
まずは、将棋の楽しさを感じることが重要です。
勉強2 囲いを覚える

自分の王様をしっかり守りましょう!
次は、王様の囲いを覚えましょう。
将棋では、王様を囲う方法が数多くあります。
特に、有名なのが「矢倉囲い」、「美濃囲い」、「穴熊囲い」などがあります。
最初に、将棋教室で教えられたのが、とりあえずどの囲いでもいいので王様を囲いましょうと教わりました。
息子と一緒に最初は、矢倉囲いを覚えました。
私は羽生先生の「羽生善治のこども将棋序盤の指し方」を購入して囲いを勉強しました。
この本は、とてもわかりやすく解説されており素人の私でも読みながら、子供に教えることができました。
勉強3 攻め方を覚える

自分の王様をしっかり守ったら、攻め方を覚えましょう!

攻め方の基本はなんですか?

まず、「棒銀」を覚えましょう!将棋の基本的な攻め方です。
これも同様に、羽生先生の「羽生善治のこども将棋序盤の指し方」で勉強しました。
とりあえず「棒銀」が、将棋の攻めの基本と教えて頂いたので、まず「棒銀」を勉強しました。
勉強4 1手詰みを始める

相手の王様を詰ますためには、詰将棋は大事です。簡単な詰将棋でもいいので詰将棋を取り組もう。
将棋を勝つためには、相手の王様を詰まさないといけません。
そのため、詰みの練習は欠かせません。
詰みの勉強法として有名なのが詰将棋です。
まず1番簡単な1手詰みから始めるのをオススメします。
私と息子は、とりあえず一番簡単な一手詰みを本で勉強しました。
その時使用した本が、羽生先生の「子ども詰将棋チャレンジ220問」を購入して勉強しました。

将棋初心者〜14級で紹介した勉強法などを詳しく知りたい方は下のリンク先の記事で詳細を解説しておりますので、ぜひご覧ください。
子供が将棋初段になるために必要なこと【14級〜10級、将棋ウォーズ4級】

引き続きいっぱい対局しよう!
将棋を楽しむことを忘れず!対局姿勢なども気を付けよう。
勉強1 とにかく対局

道場以外でも将棋を指したいけどいい方法ないですか?

将棋ウォーズっていう有名な将棋アプリがありますよ!
引き続き対局をいっぱいしましょう。
目安としては、最低でも毎日1局以上は指しましょう。このころは、指せば指すほど棋力が伸びていきます。そのため、対局をすることが棋力向上の近道です。
この頃は、とにかく対局をかなり数こなしていました。休みの日は、将棋道場で朝から夕方まで、20局ぐらい指していました。
また、将棋ウォーズをやり始めたのもこの頃です。
将棋ウォーズは、将棋アプリでアカウントを、作ると一日3局までは無料で対局ができるオススメのアプリです。
しかも友達対局なら、何度でも制限なしに対局できるので、離れていても対局が可能です。
将棋ウォーズ公式-日本将棋連盟公認-オンライン将棋ゲームの決定版 (heroz.jp)
勉強2 終盤、戦法の勉強をする。

終盤の相手の王様を寄せる方法も勉強しましょう!
序盤の定跡を覚えながら得意戦法をつくりましょう!
戦法と終盤の勉強をしましょう。
将棋には、戦法が数多くありその中から得意戦法を作ることが今後の棋力向上においても非常に、重要となりますのでしっかりと勉強しましょう。
息子は終盤での「寄せ」や「必至」の部分の指し手が不得意だったので、「羽生善治のこども将棋 終盤の勝ち方入門」の本を購入して勉強しました。
あとこの頃に、得意戦法を作った方がいいといわれたので、藤井猛先生の「四間飛車を指しこなす本」を購入して、四間飛車の定跡を覚えました。
勉強3 3手詰みを始める

1手詰みができるようになったら、次は3手詰みに挑戦してみよう!
ほぼ、一手詰みは問題なく解けるようになったので、3手詰みに挑戦しましゅう。
最初はなかなか解けないかもしれませんが、少しづつ解けるようになってくると楽しんで詰将棋ができるようになります。
息子は、ここでも引き続き羽生先生の「子ども詰将棋チャレンジ220問」で問題を解いていました。

14級〜10級になるために紹介した勉強法などを詳しく知りたい方は下のリンク先の記事をご覧ください。
子供が将棋初段になるために必要なこと【10級〜5級、将棋ウォーズ2~3級】

引き続きいっぱい対局しよう!
将棋を楽しむことを忘れず!少し難しい詰将棋などに挑戦しよう!
勉強1 やっぱり対局

上級者や有段者と駒落ち対局を積極的にしよう!
この時期もやっぱり重要なのは、対局をすることです。
特に重要なのは、上級者や有段者との駒落ち対局です。上級者や有段者の指しまわしを経験することで上達することができす。
息子も級が1桁になると、道場で上級者や有段者との駒落ち対局が増えてきました。
そのため、上級者との実力違いを感じることできました。
勉強2 5手詰みを始める

3手詰みができるようになったら、次は5手詰みに挑戦してみよう!
3手詰みが解けるようになったら、5手詰みに挑戦しましょう。
この段階でも、詰将棋が大切だというのは変わりません。
息子の昇級と解けるようになった詰将棋の時期をみると、詰将棋と棋力の相関関係や確実にあると思います。
5手詰みからは、浦野先生の「5手詰みハンドブック」で詰将棋を解くようになりました。
この浦野先生の詰将棋本は、有名で一冊で200問もあり、かなりお得意です。
緑、赤、水色の3種類がありすべて購入して、解いてました。
勉強3 歩の手筋を覚える

上級者や有段者になるためには、「歩の手筋」を覚えよう!
次に勉強することは、「歩の手筋」です。
やはり、上級者と有段者との違いは歩の使い方です。
歩の使い方で勉強する方法としてオススメなのが「歩の手筋」を覚えることです。
息子は、羽生先生の「羽生の法則 歩の手筋」で歩の手筋を勉強しました。
内容は、100のルールを局面ごとに説明してくれており、素人の私でも理解しやすかったです。
今でも、息子と読み直すこともあります。
歩の手筋の必須本といってもいいかもしれません。

10級〜5級になるために紹介した勉強法などを詳しく知りたい方は下のリンク先の記事をご覧ください。
子供が将棋初段になるために必要なこと【5級〜1級、将棋ウォーズ1級】

有段者にドンドン挑戦していこう!
勉強1 対局

一度、有段者が多い道場に挑戦してみよう!
この頃も、対局が大事だということは変わりません。
ただし、この頃からは対局の質を意識しましょう。
5級以上になれば、上級者です。とりあえ対局の数をこなすのではなく、できるだけ有段者と対局をすることをオススメいたします。
上級者になると、有段者と将棋を指してもそこそこの勝負ができるようになってきますので、有段者との差が実感出来ると思います。
息子はこの頃から有段者が多い少しレベルの高い道場に挑戦することにしました。
最初は、負けることが多かったですが、感想戦などで悪いところを指摘してもらい少しづつ勝てるようになっていきました。
勉強2 7、9手詰みを始める

5手詰みができるようになったら、次は7手詰み、9手詰みと難しいものに挑戦してみよう!
5手詰みが解けるようになったら次は7手詰み、9手詰みを解くようにしましょう。
上級者になると、読みをしっかり行わないと勝てなくなってきます。
読みを深くするためにも、手数の長い詰将棋が必要になってきます。
息子は7手詰みは、5手詰みと同じシリーズの浦野先生の「7手詰みハンドブック」を使用してました。
9手詰みに関しては、ハンドブックがなかったので、高橋先生の「9手詰将棋」を購入して、解いていました。

詰将棋を習慣にして、ライバルより強くなろう!
子供が将棋初段になるために必要なこと【1級〜初段、将棋ウォーズ初段、二段】

もう少しで初段!
しっかり対局を振り返って、1局、1局大切に対局をしよう!
勉強1 対局
この頃も、対局が大事にしていたのは変わりませんが、この段級になると有段者との平手での対局が増えてきて、1局の対局時間が長くなってきます。
そのため、集中力を持続させる必要があります。
有段者になると早指しで指しているとなかなか勝てなくなってきます。
そのため、今まで勉強した手筋や中盤でしっかり相手の手を読む必要があります。
この頃も、対局の量よりも質が大事になってきます。
勉強2 2桁の詰将棋を始める

9手詰みも大分早く解けるようになったから2桁の詰将棋に挑戦しよう!
有段者になると対局時間が長くなり集中力を持続させる必要があります。
そのため、難しい詰将棋を解いて集中力を持続させる練習をすることが、有段者ににるための近道になると思います。
詰将棋も2桁になるとかなり難しくなってくるため、1問解くのに1日かかったりすることもあります。だから集中力を持続させないと中々解けないので、集中力を持続させる練習になります。
11手詰みのために購入した本が、
「11手~15手詰パラダイス 四段以上の力をつける200題」です。
この本は、11手詰みから15手詰みまでの詰将棋の問題を収録されており、とりあえずは、11手詰みだけを解くことにしました。

難しい詰将棋と解いてライバルに差をつけよう!
勉強3 対局の振り返りをする

覚えている所まででもいいので対局を振り返れるようにしよう!
有段者になると、一局の対局を振り返って、棋譜をとることができるようになってきます。
そのため、まずは出来るところまででいいので自分の対局の棋譜をとってみよう。
息子もアマ高段の方に進められて反省の為に、負けた対局については棋譜をとってパソコンで解析をして何がダメだったか、振り返るようにしました。
振り返りをすることにより、どの戦法が苦手とかが分かるようになりました。
息子は、中飛車が不得意だったのですが対策をキッチリ勉強することによって苦手戦法では無くなりました。
特定の相手によく負ける場合は、その人が苦手ではなく、戦法が苦手の可能性があります。
そのような分析を行う上でも、振り返りは重要です。

弱点を知って、克服していこう!
子供が将棋初段になるために必要なこと【まとめ】
1、実戦対局をする

対局は初心者のころはとりあえずいっぱいして将棋の楽しもう!
上級者になってくると、すこし上の実力の人や有段者と対局をしよう!
当たり前ですがどの段級でも、実戦は大事です。
上達するコツとしては、楽しんで継続して対局することが一番です。
やはり、対局で負けてしまうと悔しくてやめようかなと思うこてゃあるし、自分が通っている道場などで負け続けると道場にいくのが嫌になってくると思います。
そういう時は、別の道場を探して行ってみるとか、将棋大会に出てみるとか出来るだけモチベーションを下がらないようにしてあげる必要があります。
息子が、昇級できなくて悩んでいた時、いつも通っていた道場から別の道場にいったりと、色々試しました。
違う道場にいくと新たな友達ができたりとすごい幅が広がりました。
2、詰将棋を毎日解く

詰将棋は将棋を強くなるために必要です。
少しづつでもいいので毎日解くようにして習慣にしよう!
詰将棋は出来るだけ毎日とくことをオススメします。
野球で例えるなら素振りやキャッチボールみたいなものです。
簡単な内は親も一緒に解いてあげるといいと思います。遊び感覚で解くと習慣化されやすいです。
私も、5手詰みぐらいまでは、一緒にどちらが早く解けるか競争しておりました。
その遊びの延長が今でも毎日詰将棋を解く習慣の要因になったと思います。
詰将棋を解くことは、将棋を上達するいろいろなメリットがあります。
◆詰みが読めるようになる。
◆読みが深くなる
◆集中力がつく
3、対局の振り返り

やはり復習は大事です!
負けた後に、対局を振り返るのは精神的にもキツイけど絶対役に立ちます!
自分の苦手戦法や、序盤が苦手なのか、終盤が苦手なのか、分析するためには必要となってきます。
仕事や勉強でもそうですが、自己分析することは、上達において非常に重要です。
この自己分析の力を、将棋で覚えれば、他の事にも必ず役に立つと思っております。
最後に
息子は将棋を本格的にやり始めた年長から、約2年ぐらいかかって、初段になることができました。人によっては、1年ぐらいで初段になる子もいるみたいです。
人によって成長速度は違いますが、続けていれば初段は十分になれると思います。
息子も3級ぐらいまではすぐになれましたが、そこから初段までは時間がかかりました。
なかなか上級者になってくると昇級が遅くなってくるので、成長を感じなくなってきますが、確実に続けるていると成長はしています。
それが、昇級としての結果につながるのは少し時間がかかる場合もあります。
今回は、親将として、息子の初段までの勉強法を基に、解説いたしました。
やはり将棋が上達するためには、どんだけ楽しみながらできるかが重要です。
親子で楽しみながら勉強してみてください。
結果は、自ずとついてくると思います。
記事を読んで頂きありがとうございました。





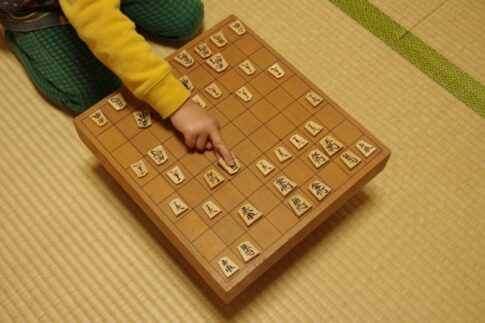
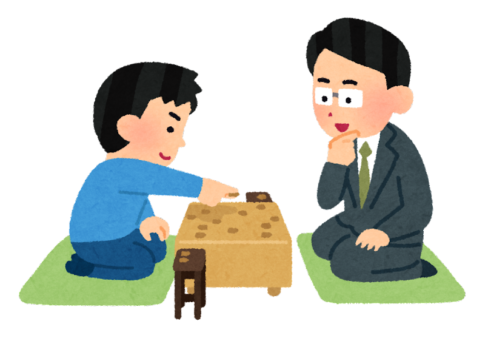




子供が将棋にハマっているけど、将棋のことは何も知らないから、勉強方法がわからない。
とりあえず初段を目指しいるが、良い勉強方法がわからない